 |
Yú Huá
|
(1960- ) |
余華小伝:余華、男、1960年生まれ。浙江海塩県の人。77年中学卒業。78年5年間歯科医として働く。83年海塩県文化館に勤務。89年嘉興市文聯に転属して今日に到る。84年から文学作品を発表し始める。『十八歳出門遠行』『偶然事件』『細雨中的呼喚』が出版されている。 (『河辺的錯誤』長江文藝出版社1992.12) 余華自伝1960年4月3日の昼頃、私は杭州のある病院で生まれた。たぶん婦幼保健医院であったと思う。当時私の母は浙江医院で、父は浙江省防疫センターで働いていた。私の生まれたときの情景について、両親は私に話してくれたことがない。私の記憶のなかでは、彼等はどちらも一日中忙しくしていて、毎日やりきれないほどの仕事があり、私は彼等に暇ができて、一緒に座って昔話や私のこと、彼等の二番目の息子のことを話すのを見たことがない。母は一度我々が杭州にいたときの話をしてくれたことがある。母はいつも懐かしく思い出すような話し方で、我々が住んでいた家や周囲の景色について話してくれた。それは私にとって大切な思い出である。杭州にいた時に過ごした短い生活は、私の想像のなかでは、幼年期、少年期を通じてもっとも素晴らしい部分でありつづけた。 父は私が1才のとき杭州を離れ、海塩という県城にやってきた。それから彼はその最大の希望を実現した。外科の医者になったのである。父は生涯で6年間しか学校に行っていない。そのうち3年は小学校、あとの3年は大学である。その間の課程は軍隊で衛生員をしているときに自習した。浙江医科大学の専門課程を修了したあと、元の免疫センターに戻りたくなかったので、外科医になるために、先ず嘉興に行った。しかし嘉興側は彼に衛生学校の教務主任をやらせた。それを嫌って彼は最終的に、もっと小さな海塩にやってきたのだった。 父は母に一通の手紙を書き、海塩をひとしきり褒めたたえたので、母は杭州での生活を放棄して、兄と私を連れて海塩にやってきた。母はよく初めて海塩に来た時の印象をこのように概括した。「自転車一台見かけやしない。」 私の記憶はこの「自転車一台見かけない」海塩から始まる。石のプレートをしきつめた大通り、横丁より狭い大通りの両側に木の電柱があって、その中からブーンブーンという音が出ていたのを覚えている。私の両親がいた病院は、一本の河によって二つに分けられ、入院病棟は河の南、問診部と食堂は北側にあった。その間を狭い木の橋がつないでいた。もし五六人が同時に上を歩いたら、木の橋は大揺れしただろう。しかも橋の面は木の板を敷いたもので、間に大きな隙間があったので、下の河の水が恐かった。夏になると、両親の同僚がよく橋の欄干のところにすわってタバコを吸いながらしゃべっていた。私は彼等が自在に太さがそろわず、しかもよく揺れる欄干の上にすわっているのを見て、とても崇高に思えたものだった。 私はよく言うことを聞く子供だった。母はよく私のことをそんな風に言った。子供の頃は大騒ぎをせず、やれと言ったことはきちんとやる子だったと。毎朝母が私を幼稚園に送っていって夕方迎えにくると、私はいつも母が帰る時に私が座っていたのと同じ位置に独りぼっちで座っていて、他の子供たちはその傍らでふざけあっているのだった。 4才になると自分で家へ帰るようになった。というか2才年上の兄が私を連れて帰ったというべきなのだが、兄はよくその仕事をなおざりにした。帰る途中で急に私のことを忘れてしまい、一人で駆け出してどこかに遊びに行ってしまったのだ。そんなとき私はずっとその位置に立って兄の帰るのを待っていたのだが、いつまで待っても埒があかないと一人で帰るしかなかった。私は帰宅の道すじを2段階に分けて覚えた。第一段階はまっすぐ病院まで行く。病院についたら今度は家までの道筋を覚える。つまり病院の向かい側の路地を入って、まっすぐに突き当たりまで行くと家に着くのだ。 次に覚えているのは、家の二階である。両親は出勤するとき私と兄を家において鍵をかけて出ていった。そこで私たちはよく窓のところに行って、外の景色をながめた。我々の住んでいたのは横丁の突き当たりであったが、実のところは単なる田舎で、私たちは長い間田んぼで働いている農民をそこから見ていた。農民の子供たちが刈った草を入れる籠をさげて、あぜ道をぶらぶら行き来していた。 夕方になって農民たちが作業を終える情景は一日のうちでもっとも面白かった。まず一人があぜ道のところに立って「あがるぞ」と叫ぶ。すると田んぼにいた人々が次々にあぜ道にあがる。次のグループが仕事の終りを叫ぶときは普通女の声である。一声かかると、また一声がやむ。見ているとその声の中を農民たちはクワを担ぎ、カラの天秤棒をかついで、三々五々あぜ道を歩いていく。続いて女たちの声が子供を呼び、籠を下げた例の子供たちがあぜ道を駆け出す。子供たちの一人か二人は大抵あまり勢いよく駆け出しすぎてあぜ道で転んでいた。 私の印象では、両親はいつも家にいなかった。あるときは一晩中私と兄の二人だけで家にいた。鍵がかかっていたので外には出られず、部屋の中で椅子などを移動させることぐらいしかできなかった。あとは二人で喧嘩をするだけだ。喧嘩になれば私が負ける。負けたら泣く、長い間泣きつづける。両親が帰ってくるまで泣きつづけて両親に兄を叱らせるのだ。一番疲れているときなので、泣いて声が枯れてしまっても両親が帰らないと、私はしかたなく寝るのだった。 その頃、母はよく病院の当直をしていた。夕方一度帰ってきた。病院の食堂で食べ物を買ってきて我々に食べさせると、またそそくさと出勤する。父はときには数日も顔を見なかった。母の話では父は手術室で病人のために手術をしているのだということだった。父はしばしば我々が寝てしまってからようやく帰ってきて、我々が起きる前にもう呼び出されて出かけていったのである。私の幼年期少年期はほとんど毎晩夢の中で「華先生、華先生、急患です」という階下の叫び声を聞いた。 兄が学齢に達すると、もう家に閉じ込められることはできなくなり、私も同じように解放された。兄は首に鍵をぶら下げ、鞄を背負って、私をつれ、学校に通う生活を始めた。兄が授業のときは、私は一人教室の外で遊んでいた。授業が終わると兄は私を家に連れて帰る。何度かは兄に呼ばれて教室に入り、兄と一緒の椅子にすわって先生の授業を聞いた。ある時女の先生が近づいてきて、兄をひとしきり叱りつけ、次からは弟を連れて学校に来てはいけないと言った。私はとても恐かったが、兄は何事もなかったように気にしていなかった。数日後、兄はまた私を授業に連れて行こうとしたが、私はきっぱり断った。あの女の先生を思い出すとどうしても行くのが恐かった。 私が小学校に入ると、同級生たちは私のことを病院のにおいがしてくさいといった。私は彼等と違い、アルコールとホルマリンのにおいが好きだった。私は病院という環境の中で育ったので、その空気になれていた。両親も両親の同僚も仕事が終わるといつもアルコールで手を消毒した。私もアルコールで手を消毒することを学んだ。 その頃は放課後になるとすぐに病院に行った。夕食の時間になるまで、病院のいろいろな片隅をぶらぶらしてまわった。私は次々と手術室から出されるバケツにはいった血と肉にまみれたものに、すっかり慣れていた。父の当時の印象でもっとも際立っているのは、手術室から出てくるときの姿で、胸の前は点々と血痕がつき、マスクを耳から掛け、歩きながら鮮血に染まった手術用の手ぶくろを脱ぐのだった。 小学校4年のとき、我々はあっさりと病院の中に引っ越して住み込んだ。我が家の向かいは霊安所で、ほぼ数日ごとに悲しい泣き声が聞こえた。数年の間に、いやになるほどの泣き声、いろいろな違った泣き声を聞いた。男、女、老人、子供のいろいろな泣き声をいっぱい。 多い時には一晩に二三回も聞こえる。私はよく夢心地から醒まされた。時には昼間でも死者の家族が霊安所で号泣する光景を見ることができた。私は腰掛けを家の戸口に運んですわり、彼等が泣きながら互いに慰めるのを見ていた。私は好奇心から何度も近づいていって死人を見ようとした。しかし残念なことに死人の顔を見ることはできなかった。私に見えたのはどれも布にくるまれた遺体で、一度だけ、そこからはみ出た手が見えたが、それはやせ細って、こころもち曲がっていた。灰白からやや黒ずんだような色に見えた。 私は子供の頃死人を見るのが恐くなかったと言わねばならない。霊安所も少しも恐くなかった。夏の最も暑いころになると、私は一人で霊安所で過ごすのが好きだった。コンクリートのベッドがひんやりして涼しかった。私の記憶では、霊安所はいつも清潔だった。周りは高い樹木に囲まれて、中には空気を入れ替えるあいたままの窓があり、夏になると外から木の枝や葉がそこから中まで伸びてきた。 私がそのころ唯一恐かったのは、暗い夜に月の光に照らされた木の梢を見ることだった。細く尖った木の梢は、月光の中できらきらと光り、空に向って伸びていく。その光景を見るたびに私は身震いがした。なぜか私にも理由がわからなかったが、どうしてもその光景を見ると恐ろしくなった。 私が小学校を卒業した年、つまり1973年のはずだが、県の図書館が再び外部に開放された。父は私と兄のために「図書貸し出しカード」を手に入れてくれたので、そのときから私は小説、特に長編小説を読むのが好きになった。あの時代のあらゆる作品にほとんど一通り目を通した。浩然の『艶陽天』『金光大道』のほかにも、『牛田洋』『虹南作戦史』『新橋』『礦山風雲』『飛雪迎春』『閃閃的紅星』……。当時私が一番好きだったのは『閃閃的紅星』で、その次は『礦山風雲』である。 そういった味気ない本を読むと同時に、私は町角の大字報に夢中になった。私はもう中学校に通っていたが、毎日放課後帰宅の途中で、必ずそういった大字報の前で一時間ばかりを過ごした。70年代中頃になると、あけすけに言えば、あらゆる大字報は人身攻撃であった。私は自分が知っている人たちが、どのように悪辣な言葉で互いに罵りあい、互いにデマをとばして相手を中傷するのか見ていた。根元を手繰って祖先の墓を暴く体のものから、色情物語をでっちあげるものまであり、いずれも漫画がついていた。漫画の内容はいっそう手広く、何でもありで、性交の格好まで描き出すものさえあった。 大字報の時代には人間の想像力は最大限度にまで発掘された。文学的なあらゆる手段が活用され、虚構、デフォルメ、比喩、諷刺など必要なものはすべてそろっていた。これが私が最初に接した文学であった。大通りの分厚く貼り重ねられた大字報の前で、私の文学好きが始まったのである。 私が実際に著作を始めたとき、私は一人の歯科医であった。中学校を卒業してから、私は鎮の衛生院(保健所と診療所を兼ねたようなものか?)に入って歯科医を始めたのである。私の同級生は皆工場に入ったが、私が工場に入らず衛生院に入ったのは、私の父が手配したのである。彼は私にも生涯医療に従事して欲しかったのだ。 その後私は衛生学校で一年間勉強した。その一年間は私にとっては大変な苦痛であった。とりわけ生理学の授業である。筋肉、神経、器官の位置などを暗記しなければならない。あまりにも無味乾燥な勉強によって、私は自分の従事する仕事に反感を持ち始めた。私は比較的自由な仕事がすきだった。想像力をもち、ふくらませることができ、気ままにすきなことができる。しかし医者になったとは言っても、私は厳密には本当の医者になったことはない。たとえ肩書きのある医者になっても、医者であるかぎり、一は一、二は二であると認めなければならない。心臓が太股のなかにあるような想像をめぐらすことはできないし、歯と足の指を混同してはならないのである。こういった仕事は厳格すぎて私には勤まらない。 もう一つは私には毎日八時間の労働には適応できない、ということである。決った時間に出勤して、決った時間に退勤するというのは耐え難いことだ。だから私が物書きに従事するようになったもっとも最初の動機は、かなりの程度、自分の置かれている環境から逃げ出したかったためである。当時の私の最大の望みは、県の文化館に就職することだった。文化館の職員を見ていると、のんびりしていて、彼らの仕事は私にはぴったりだと思われた。こうして私はものを書き始めた、しかも結構勤勉に。 作品を書くことによって、私は五年歯医者をしたのち、望みどおり県の文化館に入ることができた。その後の変化はすべて創作と関わっている。私が海塩を離れて嘉興に移ったこと、また嘉興を離れて北京にやってきたことも。 私は海塩を離れはしたが、私の作品はそこを離れることができない。私は海塩でほぼ30年生活した。私は海塩のすべてを熟知している。私は自分が成長しながら、この街の街道や河流の成長を目にしてきたのだ。海塩のどの片隅でも、すべて私は頭の中で探し出すことができる。海塩の方言は独り言のように私の口をついてでることがある。私の今までのインスピレーションはすべて海塩からのものであり、今後のインスピレーションもそこから生ずるに違いない。 いま私は北京の家で社会科学出版社の求めに応じてこの自伝を書きながら、数年前のある事件を思い出した。その頃私は県文化館に働き始めたばかりで、杭州に文学の集まりに参加したときに、黄源老先生を訪ねていった。当時もう80に近い老先生は、ふるさと海塩に小説を書く若い作家が出現したことを知って、私に手紙を下さり、私を激励するとともに、杭州に行ったら必ず忘れずに彼のところを訪ねるようにと書いてくださったのだ。 私は約束どおり出かけて行った。黄老先生は喜んで、私が海塩のどこに住んでいるのか尋ねた。私が病院の宿舎に住んでいますと答えると、病院はどこにあるかと尋ねられた。映画館の西ですと答えると、今度は映画館はどこかと尋ねる。海塩中学のそばですと答えると、海塩中学はどこだったかな、と尋ねる。 私たちの対話はこのような調子で続いたが、老先生のおっしゃる地名は私はまったく知らなかった。結局私がいとまをつげるときになっても、両方が知っている地名は一つも出てこなかった。同じ海塩の出身でありながら黄老先生のと私のは全く違った記憶のなかに存在していたのである。 思うに、また40年がたって、人の海塩から来た若者が、私と海塩の話題になったとしたら、同じようなことになるかも知れない。 (『余華作品集3』中国社会科学出版社 1995.3) |
作品集・単行本『河辺的錯誤』 長江文藝出版社 1992.12 |
     |
| 『活着』 南海出版公司 1998.5/12.00元 『許三観売血記』 南海出版公司 1998.9/16.80元 『在細雨中呼喊』 南海出版公司 1999.1/18.00元 『内心之死』 散文集 華藝出版社 2000.1/11.00元 『高潮』 散文集 華藝出版社 2000.1/10.00元 |
    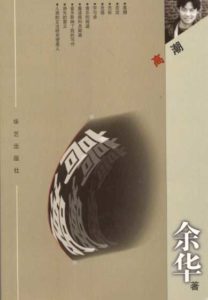 |
| 『音楽影響了我的写作』作家出版社 2008.5 『文学:想像、記憶與経験』余華等/著 復旦大学出版社 2011.3 |
  |
邦訳・単行本『活きる』飯塚容/訳 角川書店 2002.3.20/本体1500円+税 |
   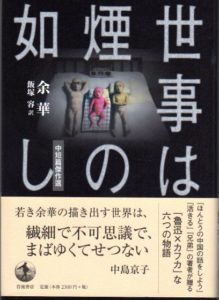  |
邦訳・作品「十八歳の旅立ち」 飯塚容/訳 『季刊中国現代小説』 蒼蒼社 |
研究資料『余華研究資料』山東文藝出版社 2006.5 |
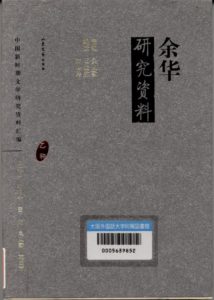  |
研究書『先鋒派作家 格非・蘇童・余華の小説論 歴史の周縁から』森岡優紀/著 東方書店 2016.11.10 |
 |
| 作成:青野繁治 |